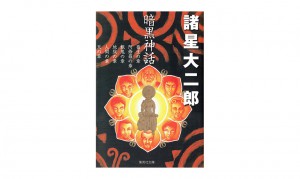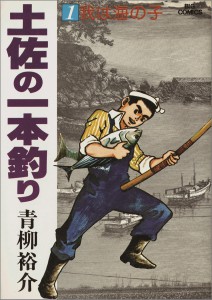2019.02.25
「これも学習マンガだ!」著者インタビューシリーズ、今回は<生活>ジャンルでの選出作品『鈴木先生』の著者・武富健治先生にご登場いただきました。異色の教師マンガが生まれた背景や作品に込められた思い、連載中の最新作についてのお話も伺っています。
(聞き手:これも学習マンガだ!事務局長/選書委員・山内康裕)
崖っぷちでの挑戦。すべてが詰め込まれた初連載だった『鈴木先生』

山内康裕(以下、山内):
『鈴木先生』は2016年度の選書で、<生活>ジャンルで「これも学習マンガだ!」に選出させていただきました。

武富健治先生(以下、武富):
ありがとうございます。(ハンドブックを見ながら)…<歴史>に『暗黒神話』が入ってる! いいですね、素晴らしいです。
教科書では触れられないことを…もちろんエンタテインメントとしてではありますけど、紹介している作品ですからね。勉強したくなるきっかけになりますよね。僕が今描いている新作も近い要素があるんですが。
山内:
そうですよね。今日は新作のお話もぜひ伺えればと思っています。よろしくお願いします。
最初に、『鈴木先生』執筆のきっかけ、背景についてお伺いできればと思います。
武富:
これは現実的な面と、自分の内面的な面と、ふたつあるんですが…まず現実的な面での話から。もともと僕は、『鈴木先生』序盤にあるような、中学生や高校生を主人公にした短編を描いていたんです。でも、これがなかなか…大手の雑誌だと、地味だということで、まず載らない、みたいな時期が長くて。
そんな中で、35歳の時に、ちょうど双葉社の「漫画アクション」が、「メッセージコミック」というコンセプトで作品を募集していたんですね。
山内:
“社会派”を打ち出してリニューアルしていた時期ですね。
武富:
そうです。ちょうど、知り合いのマンガ家さんから「武富くん、『アクション』いいんじゃない?」っていう薦めもあったので、思い切って持ち込んでみようと。
その時に、名刺代わりに短編として持っていったのが『鈴木先生』第1話の「げりみそ」というエピソードでした。

半年後、実際に掲載してもらえることになったんですが…僕としては、その短編はあくまで名刺代わりのつもりで、別の大長編を企画していたんですが、それは「つまらない」と言われてしまって。その短編をシリーズ連載にしたほうがいいという話になったんですね。
それで、たまたまその短編は珍しく先生を主人公にした謎解きという枠組みだったので、この「先生」の元でいろんな生徒の問題を扱っていくという形で、シリーズ物にできる形式になっていることに気づいて。
編集部も乗り気になってくれて、最初は短編、前後編の読み切りを毎回やっていく形だったのを、毎号連載が決定した時点で、長いエピソード、複雑な人間関係を組み合わせたエピソードに変えていったんです。
現実的な流れとしては、そんな感じでしたね。
山内:
では、内面的な流れというのは?
武富:
はい。まず、僕が中高生だった頃の学園ものって、ドラマでもマンガでも何でもそうですけど、出てくるのは不良だったり、ちょっと型破りな先生だったりで、自分みたいな生徒が主役になっている作品が少ないなと思っていて。自分で描くからには、自分のような生徒がメインになっているような作品にしたい、という思いがありました。
一方で、鈴木先生は国語の教師なので、国語教育の職業ウンチクみたいなことを描くマンガにするという案もありました。そういう路線にも興味はあったんですが…そのジャンルはそのジャンルで、もう僕よりすごいものを描く人がいっぱいいるだろうと。
それで、この作品は自分のようなタイプの読者に宛てて、ざっくりと、「人間関係」というものを見せるものにしたいなと考えて、キャラクターなんかも造型していきました。
山内:
たしかに『鈴木先生』は人間関係や、関係性によって起きる心の変化みたいなことを、すごくリアルに描いている作品だと感じます。
武富:
僕自身、20代の頃に小説、文学をよく読んでいた時期があったんですが…その頃にドストエフスキーとか、トーマス・マンとか、人間の生々しい葛藤を描く作家が好きだったんですね。その感じをマンガに持ち込めないかな、と思っていました。
山内:
たとえば学級内で行われる、いわゆる多数決というものについても、その難点や留意すべきことを含めて描かれているのも新鮮で。小中学生の子どもを持つ親御さんが読むと、すごく発見があるだろうなと思いました。
武富:
具体的なエピソードのモデルは、実は結構大人になってから、僕自身が体験した出来事だったり、問題だったりするんですけどね。20代から30代にかけて抱えていた、10代の頃にはあまりなかったような複雑な人間関係から生じた問題というものを、作品として提出したかったんです。

それで…たとえば手塚治虫先生が、現実にある差別問題をロボットと人間の関係に置き換えて『鉄腕アトム』を描いたように、大人の問題を中学生の問題に当てはめてみたらどうなるかな?と考えて。
給食だったり、掃除だったり…そういう問題に当てはめるとわかりやすくなるな、と。そういう、「寓話化」するような作業を細かくやっていきました。
ただ、もちろんそういうメッセージがあまり露骨に見えても良くないし、ある意味で説教臭いマンガではあるので、「ためになる」という部分がある一方で…。
山内;
面白さ、エンタテインメント性という部分も。
武富;
はい。気を使って…特に連載が決まってからは、できるだけぶち込むようにしていました。思春期ならではのワクワク感、もやもや感…そういう青春要素を盛り込んだり。
それはサービスではあるけど、“サービス=おもねり”ではないじゃないですか。自分自身も楽しみながら、読者も楽しませられるようにと思っていました。
山内:
終盤の、いわゆる「演劇編」も印象的でした。
僕はマンガを読む行為って、その時点である意味、キャラクターのセリフを読むことを通じてそのキャラクターを「演じ」ている状態に近いと思っているんですが、その中でさらに「演じる」という、ある意味でメタ的な構造になっているところが面白いなと。
武富:
演劇編については、1学期編までで最低限描きたかったことはひと通り出し切れたので、2学期編ではひとつ「答え合わせ」というか…応用問題で、1学期編でやったことを確認してみましょう、みたいな要素を持たせたかったんです。
それで、僕自身が…30代の頃に何年か、マンガがうまくいかなかった時期に、マンガをやめて演劇をやっていたことがあるんですね。その経験を経てマンガの作風が変わったことで、『鈴木先生』がうまくいったんじゃないかという実感があったので…それもひとつの「答え合わせ」になるな、と思ったんです。
演劇とは何か、それを経験することが人生にどれだけ影響を与えるか。それがあったから『鈴木先生』の前半は描けたんだよ、みたいなことを、ちょっとお知らせしたいという気持ちもあって。2学期はちょうど文化祭があるし、うまく入るじゃないか、と思って、まさにメタ的な感じで、「作品の中で、その作品の作り方を語っていく」みたいなことをやってみた、という感じでした。
山内:
じゃあ『鈴木先生』には、武富先生のそれまでのエッセンスがすべて入っているといっても過言ではない…。
武富:
そうです、本当にそうです。なにせ連載第1作で…それまで本当にうまくいかなかったので。その分がギャーッとめいっぱい、詰め込まれてますね。
3.11は人と社会の状況をどう変えたか。生きやすさのヒントはどこにある?

山内:
執筆や取材の中で、実際の10代の若者や子どもたちの「生きづらさ」みたいなものに触れられる機会などはありましたか?
たとえば最近は、「子どもの貧困」のような問題が社会課題として取り上げられることも多く、「これも学習マンガだ!」を一緒に展開している日本財団としても、取り組んでいる分野ではあるんですが。
武富:
『鈴木先生』の中では、そういう問題は意図的に題材として外してはいたんですけど、僕自身も、マンガ家の本そういちさんが主催している「ビースマイルプロジェクト」というNPO法人の活動に少し参加したりもしているので…関心はもちろんありますし、ほんの少しですけど、そういう問題の難しさは体感もしています。
「子どもの貧困」という問題については…僕の実感で言うと、なんかこう、昔の「貧困」と今の「貧困」ってちょっと違う気がするんですね。今って、当たり前にかかるお金がとても増えてしまっているから、最低限稼いでいても不幸な感じがあるっていうのが大きいんじゃないかなと思っていて。

東日本大震災の時に、計画停電とか、いろいろありましたよね。僕はあの時――もちろん震災そのものを良かったとはとても言えないですけど――生活を見直すきっかけとしては、とても良い機会だと思って、その後の展開をすごく期待したんですね。
というのは…それこそマンガの普及って、敗戦後の、みんなが貧しいっていう状況の中でのささやかな楽しみっていうところから始まったわけですよね。その頃のいい感じを、もしかしたら我々はもう一度体感できるのかなっていう期待があったんです。
でも、やっぱり(震災後)2,3年経った頃から急に、ぐーっと…元に、元の生活以上に戻す方向に来ちゃったな、というのがあって。
みんなで生活水準を少し下げて、みんなが質素に暮らすようになったら、弱者が減るわけじゃないですか。でも、今の世の中はそれをあくまで拒否するんだなあっていう…喪失感みたいなものが強くあったんですよね。
山内:
そのあたりで、僕の考えとしてあるのは…あの震災は各々が自分のアイデンティティをすごく意識するきっかけになったと同時に、情報網としてTwitterが注目されたこともあって、インターネット上の社会というものが顕在化するきっかけになったのかなと思って。
武富:
ああ、なるほど。
山内:
今はリアルとインターネット上とで、社会が二重構造化している状況だと思うんです。
その中でうまく自分の生活圏みたいなものを作れる人は生きやすくなっているけど、それをうまく扱えない、情報の中で溺れてしまうような人は…これは年齢にかかわらずですが、結構つらいんだろうなと。
武富:
ああー、そこはすごく重要なところかもしれません。Twitterでのやりとりを見ていても、内容とか、温度とか…はっきり分かれつつありますよね。うまく使いこなしている人と、巻き込まれてわけがわからなくなっちゃっている人と。
山内:
リアルな身体性を伴う感覚としての「まわり」と、インターネット上の「まわり」の両方があって、たとえばリアルでは都心にいるのが良いのか、地方にいるほうが良いのか。ネット上の社会ならオープンな場が良いのか、セミクローズドな場が向いているのか。そういう幅は広がっていて、ちゃんと選択できればすごく良いのかなとは思うんですが。

武富:
それこそ僕が演劇で学んだことでもありますけど、その、いわゆる身体性みたいなことを意識できると、人間関係もとても、こう…なめらかになるんですよね。
昔はいわゆる「頭でっかち」というか、勉強が得意なヤツはそういう「人との関わり」がうまくなくて、そうじゃない人のほうがうまいと言われていて、対立するような構造がありましたけど…今は、もうそれには関係なく下手な人は下手であるということが露呈してきて、そういう対立もなくなってきていると思うので。
そういう状況も作用して、自然に変わっていくといいなあとは思うんですよね。
話を戻すと、子どもの問題にも、結局はそういった大人の自己変革が浸透していくと思うので。しかるべき機関が具体的な子供の貧困対策をしてくれている間にも、大人は安心してまかせっぱなしにしたり気分で口をはさんだりして済まさずに、ひたすら自分たちを変えていかないといけないなっていうのが、自分の中では大きいですかね。
デジタル配信時代だからこそ、年代にとらわれない「特殊な出会い」が可能に

山内:
武富先生自身が、「学び」を得る経験をしたマンガはありますか?
武富:
選ぶのが大変なくらいなんですが…(笑)。
基本的に僕が描くマンガで目指しているのは、自分が子どもの頃や若い頃にマンガを読んで受けた衝撃…「こんな世界があったのか」というような、ある意味「大人っぽくなれる」衝撃を感じさせることなんです。そのモデルになっている作品がいくつかあるんですよね。
最初は、それこそ『ドラえもん』とか…ちょうど「コロコロコミック」が創刊されたばかりだったので、そういう児童向けに描かれたマンガを読んでいたんですが、その中に『ゲッターロボ』という作品があって。もともとはアニメを見ていて、それはふつうに子供向けだったんですが…そのマンガ版があったので、ちょっとおねだりして買ってもらったんですよ。
そうしたら、マンガのほうは…永井豪先生、石川賢先生が描かれてたんですけど…結構、すごい内容で(笑)。
山内:
そうですよね(笑)。
武富:
小学校1年生とかでしたから、すごい衝撃を受けて…完全には理解できなくても、夢中になったんですよね。それから『デビルマン』を読んだり、中学年になると『火の鳥』を読んだりしました。
そういう中で、中学に入る頃には古本に手を出し始めて…もちろん当時の、自分の世代向けのマンガも読んでいたんですけど、あえて少し昔のマンガを探して読んでいく、みたいな作業をするようになったんですね。
その時に出会って特に衝撃を受けたのが、白土三平先生の『カムイ伝』と、永島慎二先生の『漫画家残酷物語』のふたつです。

どちらも、当時としても少し前の時代の物語なので、生活感覚は違ってはいたんですけど、その中ですごく大事なものを発見した感触があって。
それは後々、文学を読む時にも「今の自分に足りないものを得たい」という感覚を持つようになったきっかけでもありましたね。
マンガを読むきっかけって、流行っているからとか、友達が読んでいるからっていうのが多いと思いますけど…そういう、「自然に口を開けていれば入ってくるようなもの」以外に対しての渇望、みたいな感覚が10代のうちに芽生えていると、大人になるまでに得られるものが結構、違ってくるんじゃないかと思います。
山内:
よくわかります。このプロジェクトでも、昔の作品も、今の読者が読むことで新たな発見があるんじゃないかという思いもあり、過去の作品も選書対象に入れながら、バランスを考えて検討しています。
武富:
『土佐の一本釣り』とかも入ってますもんね。素晴らしいですね!
子どもは古いものを読まないからといって、全部新しいものにしてしまうと、そういうきっかけがどんどん失われてしまいますよね。
大人が、自分が昔好きだったものを紹介するのって、あまり押し付けがましくやると失敗しちゃうと思うんですけど…押し付けるんじゃなく、自然に置いておいて手に取らせるみたいな、そういう環境が、いわゆるマンガ読みじゃない人に対しても、あるといいなあと思いますね。
山内:
今は電子書籍もありますからね。

武富:
そうですよね。電子書籍の一番良いところは、過去の作品を広められるというところかなと思います。それに、やっぱりデジタル配信なんかの影響もあるんだと思いますけど、最近はマンガのアニメ化もいろんなタイミングでされていますよね。ちょっと前だったら、連載が終わってしばらく経ったらもうチャンスはない、みたいな感じでしたけど。
これまでにも――90年代くらいから、昔のマンガを振り返る動きは時々あったと思いますけど、僕が挙げた白土三平さん、永島慎二さんは、なんかそういう動きからちょっと、漏れている感じもあって…。アニメにもならないし。
『カムイ伝』、アニメにするといいと思うんだけど(笑)。
山内:
ある意味、コンテンツが溢れている時代ですから…いろんな形で、過去の作品にも触れてもらえるきっかけが増えるといいなと思いますよね。
少し最近のマンガではいかがですか?
武富:
そうですねえ…僕はちょっと嫉妬心が強くて(笑)、悔しいって思っちゃうことが多いんですけど…たとえば同時期にずっと「アクション」で描かせてもらっていた『この世界の片隅に』のこうの史代さんは、やっぱり素直にすごいなと思えました。実験的な部分も含めて、僕が選ばなかった方面にマンガの可能性を広げていらっしゃる感じもして。
それこそあの作品も、連載が終わってかなりしばらくしてからアニメ映画で話題になりましたけど…こうのさんに陽が当たる世の中になるというのは、個人的にはすごく、励まされますね。
山内:
武富先生もこうの先生も、それぞれお互いにない部分が個性となっている作風で、どちらもそれぞれ魅力的だと感じます。
最後に、せっかくなので新作についても少しお話しいただければ。
武富:
はい。今連載中の『古代戦士ハニワット』は、もともと子どもの頃に描いていたマンガで、大人になってからもう一度ちゃんとやりたいなと漠然と思っていた作品です。
『鈴木先生』の7,8巻くらいの頃、編集さんとの間で「そろそろ次を考えようか」という話になった時に提出した案でした。その後にいろいろ他社さんとの約束が入ってしまっていたので間が空いてしまったんですが、「次は『ハニワット』ね」という約束は当時からできていて。
久々のオリジナルなんですよね。『鈴木先生』以降は、自分ひとりでは描けないものを描いてみたいという思いもあって、原作付きとか、原案協力をいただいた作品が続いていたので…そこで培ったものを、いよいよ反映させてみようと。

山内:
少し拝見して、ゾクゾクする感じと、エンタテインメントの混ざり具合がすごいなと思いました。
武富:
いわゆる“変身もの”ではあるんですけど、自分としてはやっぱり、そのジャンルの枠組みを越えるものにしたい思いが強くて。変身ものという意味でも、アクションマンガという意味でも、「こういうのが欲しかったんだよね!」っていう思いを、濃密に突っ込んでいます。
読者さんに「これ、期待してなかったけど、読んでみるとすごく面白い」と思ってもらえるようなものにはなってるんじゃないかなと。そういう意味では、全然興味がない人にも読んでほしいなあ。幅広く楽しんでもらえるように、いろんな要素を盛り込んでいるので。
その一方で、表現上あえて抑制した手法とか、要素っていう部分もあります。2回、3回と読み返した時に「あ、そういえばこの要素を使っていないのに面白いな」と気づいてもらえるような…そういう面でもいろいろこだわっているので、マンガ表現そのものに興味がある人もぜひ。
山内:
僕も個人的にもワクワクしている作品なので、楽しみです。
本日はありがとうございました!

(2019.1.16. 武富先生仕事場にて)
****
【プロフィール】
武富健治(たけとみ・けんじ) マンガ家
佐賀県生まれ。97年に『屋根の上の魔女』でマンガ家デビュー。2006年より連載開始された『鈴木先生』が話題となり、実写ドラマ化・映画化。07年、同作で文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。原作付き作品も幅広く手がけており、2017年には『火花』(原作:又吉直樹)のコミカライズを担当。2019年2月現在、最新作『古代戦士ハニワット』を「漫画アクション」(双葉社)にて連載中。
山内康裕(やまうち・やすひろ) これも学習マンガだ!事務局長/選書委員
1979年生。法政大学イノベーションマネジメント研究科修了(MBA in accounting)。
2009年、マンガを介したコミュニケーションを生み出すユニット「マンガナイト」を結成し代表を務める。また、2010年にはマンガ関連の企画会社「レインボーバード合同会社」を設立し、“マンガ”を軸に施設・展示・販促・商品等のコンテンツプロデュース・キュレーション・プランニング業務等を提供している。「さいとう・たかを劇画文化財団」理事、「これも学習マンガだ!」事務局長、「東アジア文化都市2019豊島」マンガ・アニメ部門事業ディレクター、「立川まんがぱーく」コミュニケーションプランナー等も務める。共著に『『ONE PIECE』に学ぶ最強ビジネスチームの作り方(集英社)』、『人生と勉強に効く学べるマンガ100冊(文藝春秋)』等。